消費税の端数処理は切り捨て・切り上げ、どっち?インボイス制度でどうなる?
消費税の1円未満の端数は、切り捨てても、切り上げても、四捨五入しても構いません。消費税の端数処理の考え方と、インボイ…[続きを読む]
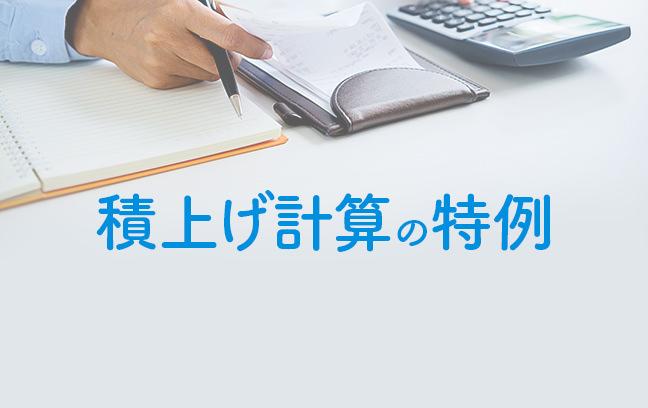
消費税額の計算には様々な特例があり、積上げ計算の特例もそのうちの一つです。売上の税額を計算する際、積上げ計算のほうが有利になることもあります。
この特例は、すでに廃止され、経過措置で認められていましたが、インボイス制度の導入に伴い、再び正式に認められるようになりました。
積上げ計算とはどんなものか? 今までの経緯、計算方法、積上げ計算の注意点などを解説します。
目次
消費税の「積上げ計算」とは、消費税申告時に納税する消費税を計算するときの計算方法です。取引で請求書や領収書を作成するときは関係ありません。
消費税申告時の消費税額計算の原則は次の通りです。
まず、すべての課税売上の合計額を計算し、そこに、100/110、78/100をかけて、割り戻すことから「割戻し計算」と呼ばれています。
原則計算の一方、消費税は積上げ計算の特例で税額を求めることも認められています。
積上げ計算とは、税抜価格を前提に、一取引単位の消費税額を積上げて計算する方法をいいます。
このような特例が設けられている理由は、取引金額が少額である商品を大量に取引する業態だと、販売の都度端数処理をした1円未満の金額が膨大になってしまうためです。
【例】本体価格499円の商品の場合
1回の取引では1円の差しか生じませんが、このような少額な取引を大量に行う事業者の場合、積み重なって大きな差が生じる可能性があります。
このような事態を想定して規定されたのが積上げ計算の特例なのです。
一般消費者が主な取引相手となる小売店などでは、積上げ計算の特例により消費税額を算出した方がお得なケースも多くなります。
なお、積上げ計算の特例を適用するためには、領収書等に消費税額が記載されていることが条件となります。
積上げ計算の特例は、総額表示方式の導入により2004年(平成16年)4月に廃止されました。
総額表示方式とは、店によって表示価格が税抜きだったり税込みだったりと消費者を混乱させる価格表示を避けるため、消費税込みの金額を表示することを義務付ける制度です。
ただし、総額表示方式の特例として税抜き表示することも、2021年3月まで認められていました。
それに伴い、積上げ計算の特例の廃止にも経過措置が設けられ、今までずっと続いていました。
原則の割戻し計算と、特例の積上げ計算で、消費税額が異なるのは、1円未満の端数処理から生じる問題です。
ここまで読んで「消費税額の端数処理に規定はないの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。
実は消費税の端数処理方法には法律の規定はありません。
切り上げ、切り捨て、四捨五入、どの方法を選択するかは販売者側が自由に決めることができるのです。
ただし、消費者が相手では、消費税額の端数は切り捨てが一般的です。
また、事業者間の取引ではトラブルを避けるため、事前に消費税額の端数処理について取り決めを交わすこともあるようです。
ここで、先ほどの例を利用して計算方法ごとの税額の違い確認しておきましょう。
考えられる計算パターンは下の表のとおり4通りあります。
本体価格499円×1.1=548.9円の端数処理方法別に下の表を参考にしてください。
| 計算方法 | 税込価格 | 消費税額 | 課税標準額に 対する消費税額 |
|---|---|---|---|
| 積上げ計算(切り捨て) | 548円 | 49円 | 49,000,000円 |
| 割戻し計算(切り捨て) | 548円 | 49円 | 49,818,100円※ |
| 積上げ計算(切り上げ・四捨五入) | 549円 | 50円 | 50,000,000円 |
| 割戻し計算(切り上げ・四捨五入) | 549円 | 50円 | 49,909,000円※ |
※計算の詳細は、本記事の最後の「割戻し計算の計算方法」に記載しました。
このように比較すると、消費税の端数を切り捨て処理した場合、積上げ計算の特例の方が原則の割戻し計算より有利なことが分かります。
ただし、端数処理を切り上げている場合は、逆に、積上げ計算の特例の方のほうが不利になってしまいます。
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。インボイス制度では、積上げ計算の特例が新たに規定され、正式に再び特例となりました。
従来の積上げ計算の経過措置とは違って、次のような要件があります。
売上税額の計算について、原則は割戻し計算ですが、インボイス発行事業者であれば、積上げ計算も可能です。
逆に、免税事業者は、積上げ計算ができず、割戻し計算しかできません。
仕入税額の計算について、原則は積上げ計算ですが、特例として、割戻し計算も可能です。
ただし、売上税額を積上げ計算する場合、必ず仕入税額も積上げ計算する必要があります。売上だけ積上げ計算して、仕入を割戻し計算すれば、売上税額の消費税は低く、仕入税額の消費税は高く計算され、納税額を少なくできてしまうからです。
一方、売上の消費税額に関して積上げ計算をするときは、仕入の消費税額に関しても、積上げ計算をする必要があります。
売上・仕入それぞれの割戻し計算・積上げ計算の組み合わせを表にまとめました。
| 売上 | 仕入 |
|---|---|
| 【原則】割戻し計算 | 【原則】積上げ計算 |
| 【特例】割戻し計算 | |
| 【特例】積上げ計算 | 【原則】積上げ計算 |
①まずは、課税売上高合計の税込価格から税抜金額を求めます。
548円×100万個=548,000,000円
548,000,000×100/110=498,181,818円
②税抜処理した金額の千円未満を切り捨て、課税標準額を求めます。
498,181,000円(課税標準額)
③課税標準額に7.8%(税率10%)を乗じて、課税標準額に対する消費税額を求めます。
498,181,000円×7.8%=38,858,118円
④上記金額の22/78(税率10%)を乗じて、課税標準額に対する地方消費税額を求めます
38,858,118円×22/78=10,959,982円
⑤消費税額と地方消費税額を合計します。
38,858,118円+10,959,982円=49,818,100円
①まずは、課税売上高合計の税込価格から税抜金額を求めます。
549円×100万個=549,000,000円
549,000,000×100/110=499,090,909円
②税抜処理した金額の千円未満を切り捨て、課税標準額を求めます。
499,090,000円(課税標準額)
③課税標準額に7.8%(税率10%)を乗じて、課税標準額に対する消費税額を求めます。
499,090,000円×7.8%=38,929,020円
④上記金額の22/78(税率10%)を乗じて、課税標準額に対する地方消費税額を求めます
38,929,020円×22/78=10,979,980円
⑤消費税額と地方消費税額を合計します。
38,929,020円+10,979,980円=49,909,000円