確定申告の必要書類・添付書類まとめ
確定申告で必要な書類は人によって異なります。この記事では、確定申告で必要となる書類をケースごとに整理して紹介します。[続きを読む]
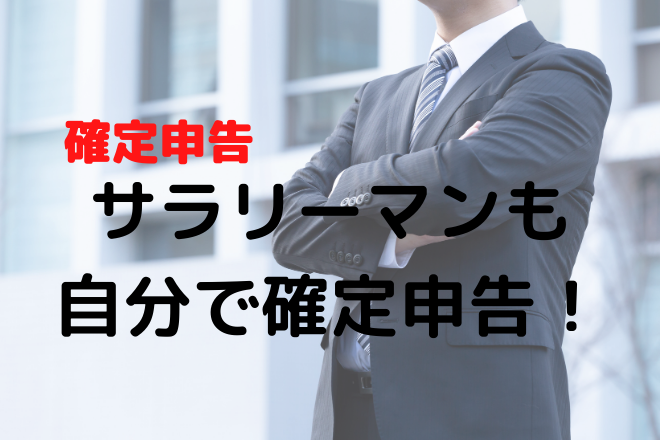
マイホームを買ったりふるさと納税をしたりした方の中には会社で年末調整を受けても確定申告が必要になることがあります。
この記事では会社員でも確定申告が必要になるケースについて解説します。
サラリーマンが確定申告しなけれならないのはどのようなケースなのでしょうか?
条件を確認していきましょう。
サラリーマンで確定申告が必要となるケースには、次のものがあります。
2カ所以上から給与をもらっている人のうち、2か所目の給与収入が20万円以下の方は確定申告は不要です。
また、副業収入は雑所得として確定申告を行いますが、雑所得が20万円以下の場合は同様に確定申告は不要となります。
その他にも、以下のような特殊な方も確定申告が必要となります。
確定申告をする義務がない方でも、以下に該当する方は確定申告をした方がお得になる可能性があります。
年末調整で利用できなかった控除を利用したり、株取引や不動産収入で損失が生じている方は、確定申告をすることで税金の還付を受けることができたり、損失の繰り越しをすることができます。
ここからはサラリーマンが実際に確定申告を行う方法について解説していきます。
まずは確定申告の手順を簡単に見ていきましょう。
ごくごく簡単に言えば、上記の流れで確定申告を行います。それぞれの詳細についてはこの後解説します。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日ですが、受付開始日と最終日が土日の場合は週明けの月曜日にずれ込みます。
ただし、確定申告を行うことで税金が還付になる人の場合は、その年の翌年1月1日から5年間が確定申告期間となります。
還付申告を行う予定の方はなるべく早く申告した方が早めに還付金を受け取ることができます。
確定申告で必要となる書類をケースごとに解説していきます。
まずは確定申告を行うサラリーマンが誰でも必要となる書類を挙げます。
以前、確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、会社員の場合はAで申告することが多かったと思います。ですが、2023年以降確定申告書A・Bという区分けははなくなり、書式は1種類に統一されました。
源泉徴収票は税務署に提出する必要はありません。しかし、源泉徴収票に記載されている情報を確定申告書に転記する必要があるため、ある意味必須と言えます。
本人確認書類はマイナンバーカードか、それがない方はマイナンバーが確認できる書類に加えて運転免許証やパスポート等の書類が必要となります。ただし、e-Taxで電子申告する場合には本人確認書類の添付は不要です。
確定申告では所得の種類や利用する控除によって必要書類が変わります。ケースごとの必要書類の一例を表にまとめました。
| ケース | その他の必要書類 |
|---|---|
| 年金収入がある人 | 公的年金等の源泉徴収票(添付不要) |
| 不動産を売却した人 | 確定申告書第三表 譲渡所得の内訳書 登記簿謄本 不動産取得時の売買契約書等 不動産売却時の売買契約書等 |
| 株取引で譲渡益が生じている人 | 確定申告書第三表 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 年間取引報告書等 |
| 満期保険金を受け取った人 | 満期保険金支払証明書 |
| 医療費控除を受けようとする人 | 医療費控除の明細書や医療費通知 |
| ふるさと納税を行っている人 | 寄附金受領証明書 |
| 住宅ローンを組んで家を購入した人 | 住宅借入金等特別控除額の計算証明書 登記事項証明書 売買契約書 年末残高証明書 |
上記以外の所得が生じている方や、他に利用する控除がある方はまたそれぞれ別の書類が必要となります。
確定申告書には、以下のような情報を記入します。
詳しくは下記の記事で記入例・図解込みで解説していますので併せてご覧ください。
確定申告書の提出方法には以下の3種類があります。
郵送による提出の場合は消印が押印された日が提出日となります。
e-Taxでオンライン申請する場合は税務署でID・パスワードを発行するか、マイナンバーカードをカードリーダで読み込んで行います。提出方法の詳細は以下の記事を参照してください。
ここからはサラリーマンの確定申告についてよくある質問と回答をまとめました。
個人年金を支払った場合と、受け取った場合のそれぞれについて解説します。
まず、個人年金を支払っている方は生命保険料控除を利用できます。ただし、年末調整で控除を利用している方が再度確定申告で控除を利用することはできません。
一方、個人年金を受け取った場合はその収入について確定申告をしなければなりません。ただし、年金の受け取り方法や誰が受け取るのかによって申告内容が変わります。
年金形式で受け取る場合は「雑所得」として申告し、一括受け取りの場合は「一時所得」として申告します。
副業収入がある方は、収入の形態によって確定申告の方法が異なります。
副業収入を給与で受け取っている人は「給与所得」として確定申告を行います。ただし、副業の給与収入が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
副業でブログ運営等を行いアフィリエイト収入がある人や、ライター業など報酬形式で副業収入を得ている人は「雑所得」として確定申告を行います。ただし、年間の雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。雑所得の金額は「収入-経費」で算出します。
確定申告では、サラリーマンが経費を申請できる「特定支出控除」という制度があります。「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費 」「帰宅旅費 」「図書費」「衣服費 」「交際費等」といった支出が経費として認められており、この経費は給与所得から控除されます。
ただし、特定支出控除の適用には「支出金額が給与所得控除額の1/2以上」といった金額の要件や、勤務先の承認を得ること等、一定のハードルがあります。該当しそうな方は確定申告を検討してみてはいかがでしょうか。
サラリーマン大家として不動産賃貸収入を得ていて、不動産所得が20万円を超える人は確定申告の必要があります。また、不動産所得が20万円以下であっても、不動産所得がマイナスになる方は確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
不動産所得の申告には白色申告の場合は「収支内訳書(不動産所得用)」、青色申告の場合は「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」が必要となります。
これらの書類で不動産収入の年間の合計額と必要経費の金額を集計して不動産所得を算出します。また、収入の内訳や減価償却の計算などもこの書類上で行います。
不動産所得の申告で必要経費として認められる代表的なものは以下の支出です。
上記以外にも不動産所得に関連した支出がある場合には経費計上が可能です。
なお、不動産所得があるサラリーマンが青色申告を選択した場合、65万円または10万円の控除を受けることが可能です。65万円控除を受けることができるのはいわゆる「5棟10室」の基準を満たしている事業的規模で不動産賃貸を行っている人のみです。したがってほとんどのサラリーマンは10万円控除を選択することになると言えるでしょう。
住宅ローンを組んで土地・建物を取得した場合には、確定申告を行うことで「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目からは年末調整で控除を受けることができます。
逆に家を売却した場合には、売却益が生じた場合に限り譲渡所得として確定申告が必要となります。売却益は「売却代金―(家の取得費+諸経費)」で計算します。
家を売っても売却益が生じなかった場合は確定申告の必要はありませんが、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。申告を検討してみることをおすすめします。
車を売却した際の収入は確定申告が必要なケースと必要ないケースがあります。
まず、日常生活で普通に使用していた車を売却した場合の収入は、所得税は非課税とされています。したがって確定申告の必要はありません。
確定申告が必要となるのは、嗜好性の高い車を売却した場合です。例えば希少価値の高い車やスポーツカーなどは「日常生活に通常必要なもの」とは見なされずぜいたく品という扱いになるため、確定申告が必要となる場合があります。また、キャンピングカーなども同様の理由で確定申告が必要となる可能性があります。
ただし、確定申告が必要となるのは売却益が50万円超生じた場合のみです。
ふるさと納税をしている人が寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
ただし、ワンストップ特例制度を利用している人は確定申告の必要はありません。ワンストップ特例制度は確定申告に比べて手続きが簡易的なので、サラリーマンの方にはお勧めの制度です。
ただし、ふるさと納税の申し込み先が6自治体以上ある人はワンストップ特例制度を利用することができません。そういった方は確定申告で控除を利用することになります。
なお、例えば「ふるさと納税をした6自治体のうち、5自治体はワンストップ特例制度の申請をした」という方は、6つすべてのふるさと納税について確定申告をする必要があります。ふるさと納税先が6自治体以上となった場合はワンストップ特例制度の申請がすべて無効となるためです。
株取引とFXの確定申告についてそれぞれ簡単に解説します。
株取引で譲渡益が生じている場合、譲渡所得として確定申告をする必要があります。ただし、株取引の確定申告は口座の種類によって表の通り対応が変わります。
| 口座の種類 | 確定申告の要否 | |
|---|---|---|
| 一般口座 | 確定申告が必要 | |
| 特定口座 | 簡易申告口座 | |
| 源泉徴収口座 | 確定申告不要 | |
このように特定口座のうち源泉徴収口座で株取引を行っている人以外は、確定申告をする必要があります。特定口座の源泉徴収口座は売却益が生じるたびに源泉徴収がされているため、確定申告は不要です。
ただし、株取引で譲渡損が生じている方は損失を3年間繰り越すことができます。したがって源泉徴収口座であっても譲渡損がある方は確定申告をした方がお得となります。
FXによる利益が20万円超出ている人は、雑所得として確定申告をする必要があります。その他の雑所得と異なる点は、FXによる所得は「分離課税」となる点です。
FXも株式と同様に、損失が生じた場合は3年間繰り越すことが認められています。
確定申告は「青色申告」と「白色申告」を選択することができます。
青色申告は事前に税務署に承認申請書を提出しなければならないことや、複式簿記により記帳しなければならないという手間は生じますが、節税に効果的な様々なメリットを享受することができます。
「節税効果がある」と聞くと青色申告を選択したくなってしまうと思いますが、サラリーマンの方は白色申告を選択した方が良い場合もあります。なぜなら青色申告の対象となる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみだからです。
サラリーマンの副業は事業所得とはならず、雑所得となることがほとんどです。要するにサラリーマンのうち青色申告を選択すべき人は「不動産所得がある人」ということになります。それ以外の方が青色申告を選択しても手間が増えただけで節税効果が全くないといったことになりかねません。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます
確定申告シーズン付近に転勤等の理由で引っ越しした場合、どのように確定申告を行えばよいのでしょうか?
まず問題となるのは確定申告書の提出先です。原則として確定申告書は、確定申告を行う時点で住んでいる場所で行います。したがって提出先は「確定申告時点で住んでいる場所の管轄の税務署」となります。
なお「引っ越したけど住民票は移していない」という方も同じく「確定申告時点で住んでいる場所」で確定申告を行います。確定申告書に記載する住所も実際に住んでいる場所です。
この記事を簡単にまとめていきます。
サラリーマンで確定申告が必要になる例のうち、よくあるのは次のパターンです。
確定申告書に源泉徴収票の内容を転記し、その他必要情報を記入して税務署に提出します。
事業所得などがなければスマホで確定申告書の作成から提出まで済ませることも可能性です(e-Tax)。
最後まで読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。
これらの記事を読んで、確定申告でつまずかないようにしましょう!
【関連記事】