【令和5年分】確定申告書の書き方(会社員・サラリーマン向け)
2023年2月16日~3月15日に行う、令和4年分の確定申告書の書き方について、会社員・公務員・サラリーマン向けに、…[続きを読む]
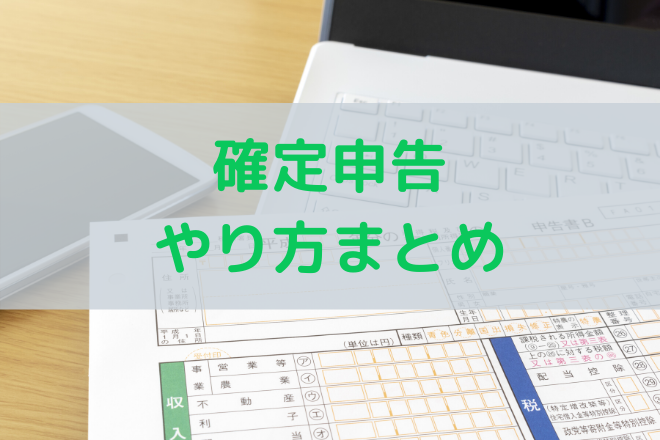
最近では、確定申告をオンラインで済ませる方が増えてきました。オンラインで申告書の作成ができるだけでなく、「マイナポータル連携」など、必要事項の入力を省略できる機能も年々充実しています。
この記事では確定申告のやり方をまとめてご紹介します。確定申告書の作成方法、そして提出方法を具体的にあげていきます。ご自分に合った方法を見つけるのに役立ててもらえればと思います。
目次
確定申告を行なう手順には以下の3つのステップがあり、基本的に2月16日から3月15日までにすべて完了させる必要があります。
各手順にはそれぞれいくつかの方法がありますので、早速確認していきましょう。
申告書を作成する方法としては以下の5つがあります。
なお、いずれの方法を選ぶ場合も作成を始める際は以下のような書類を用意しましょう。
確定申告書には前年の収入を記載する必要があります。給料をもらっている人は勤務先から渡される源泉徴収票に、個人事業主の方などは支払調書に記載された「支払い金額」を確定申告書に転記します。
確定申告書には納税者のマイナンバーを記入する必要があります。配偶者(特別)控除を受ける方などは配偶者のマイナンバーも必要です。
保険料控除などを利用する方は、確定申告書に前年に支払った保険料やそれをもとに計算した控除額などを記載する必要があるため手元に控除の証明書を用意しておきましょう。
控除などを利用して税金が還付(返金)になる場合、振込先の口座番号を記入する必要があります(公金受取口座への入金を希望する場合は不要)。
確定申告を手書きで行う場合、以下のいずれかの方法で確定申告書を用意して必要事項を記入していきます。
確定申告を手書きで行いたい場合、こちらの記事にて書き方を紹介しているので、ぜひご参照ください。
「確定申告書等作成コーナー」とは国税庁が提供しているオンラインツールで、アンケートに答えるように、指示された項目を順番に入力していくだけで申告書類が作成できます。
作成した申告書は印刷して提出する他、e-Taxを利用すればオンラインでも提出可能です。
確定申告書を手書きする場合、収入などをもとに自分で税金の計算をする必要がありますが、確定申告書作成コーナーを利用すれば計算は自動で行ってくれるので計算をミスしてしまうリスクがありません。詳しい使い方は下記の記事で解説していますので併せてご覧ください。
また、確定申告書作成コーナーは、スマホ・タブレットでも利用できます。
市販の「確定申告ソフト」を利用する方法もあります。確定申告だけでなく日々の会計業務も行えるタイプのソフトもあるので大変便利です。
作成した申告書は基本的に印刷して提出しますが、「Freee」であればオンラインでの提出(e-Tax)も可能です。
確定申告を確定申告で行うメリットとしては、大きく分けて二つあります。
先述のFreeeなどは質問に答えていくだけで確定申告書を作成できます。また、プランにもよりますが、確定申告ソフトはチャットや電話、画面共有などのサポートが充実していますので初心者でもつまづきにくいでしょう。
確定申告ソフトにはFreee以外にも弥生など様々な種類がありますので、選び方に迷う方は下記の記事をぜひご参照ください。
確定申告ソフトを利用する場合、パッケージ型の確定申告ソフトであれば購入時に10000円から20000円程度、クラウド型の確定申告ソフトであれば、月額で1000円から3000円程度が必要になります。
ですが、確定申告ソフトの中でも大手の「弥生」では確定申告ソフトを1年間無料でお試し利用することができますので特に個人事業主の方や安定した副業収入がある方などは一度試してみるのもおすすめです。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
確定申告にお金をかけたくない場合や、毎年確定申告をするわけではない場合などはまずは先ほど紹介した確定申告作成コーナーなどを試してもいいでしょう。
なお、確定申告ソフトについては下記の記事でもう少し詳しく解説していますので、使うべきか迷う方は是非ご覧ください。
上記いずれの方法でも難しいという場合は必要な書類をもって税務署に行き、職員の方に相談しながら作成する方法もあります。
なお税務署は基本的に平日のみの開庁(確定申告時期は特別日程を敷いている税務署もあります)な点には気を付けましょう。また、必要な書類や印鑑などは忘れずに持参しましょう。
確定申告は税理士に代行してもらうことが可能です。当然費用は掛かりますが、本業に専念したい事業者の方などは検討の余地があるでしょう。
なお、税理士以外に確定申告書を作成してもらうのは法律違反なので気を付けましょう。
作成した申告書を提出する方法は以下の三つです。
なお、税務署に提出しに行く場合、あるいは郵送の場合、確定申告書の提出の際は以下の書類を添付する必要があります。
また、どこの税務署に提出すればいいかわからない方は下記の記事を参照してください。
作成した確定申告書と添付書類をもって税務署の窓口に持参します。初めて確定申告をされる方は窓口に持参し、書類を確認してもらうとよいでしょう。
ただし、税務署の開庁時間は平日のため、確定申告の期間中に税務署に行ける時間をあらかじめ作る必要があります。
確定申告に慣れている方であれば、税務署に置いてある申告書の提出ボックス(時間外収受箱)に投函することも可能です。
税務署の開庁時間に確定申告をしに行くことが難しい場合は確定申告書を郵送することも可能です。
申告書は「簡易書留」「信書便物」によって提出し、「消印」の日付が提出日とみなされます。
e-Taxとは、インターネットを使って申告データを電子送信できる国税庁のシステムのことで、先述の「確定申告等作成コーナー」あるいは一部の確定申告ソフトで作成した申告書のデータをオンラインで提出できます。
e-Taxを利用すると申告書の作成から提出までオンラインで完結します。また、窓口提出や郵送と違い添付書類の提出が不要となります。
また、青色申告をする場合、2019年までは65万円の特別控除額がありましたが、2020年分から55万円に減額されてしまいました。しかし、e-Taxを利用して申告した場合は引き続き青色申告の特別控除額が65万円のまま減額されません。
e-Taxにて電子申告することのデメリットは、準備に手間やコストがかかることです。税務署に行かずに確定申告を完了させるには最低でも下記が必要です。
上記が用意できない場合、「ID・パスワード方式」を利用できますが、一度税務署に行ってID・パスワードを発行してもらう必要があります。
確定申告で還付を受ける方は申告書に記入した口座に還付金が振り込まれるのを待つ形になりますが、確定申告で税金の支払いが生じた方は期限までに納税をする必要があります。
納税方法には以下の方法がありますが、詳しくは下記の記事をご確認ください。
今回ご紹介したように、現在、確定申告は様々な方法で行えるようになっています。税金の支払いが発生する方はもちろん、還付を受けられる方も、ご自分に合った方法を選んで期限内に申告を行うようにしましょう。