医療費控除の対象となるもの/対象外となるものの範囲一覧
医療費控除の対象となる医療費と、対象外となる医療費の違いを、解説するとともに一覧にまとめました。[続きを読む]
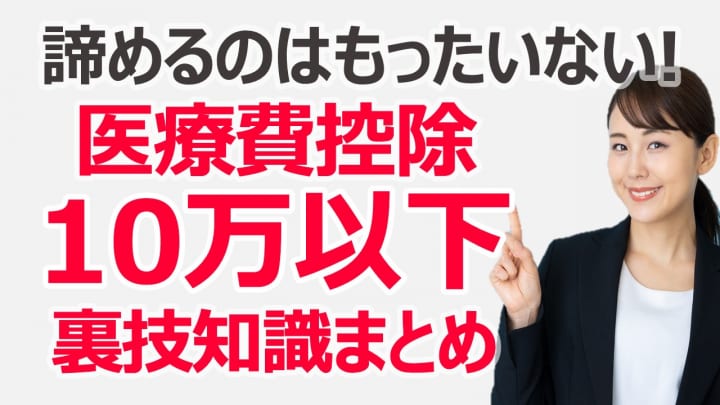
医療費の支払いが多いと利用できる「医療費控除」。けれど「去年の医療費を全部あわせても10万円いかなかったし……」と諦めてしまっている方、「医療費が10万円ちょっとだと意味がないかな?」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では「医療費が10万円以下でも医療費控除が利用できる条件」や「医療費が10万以下、あるいは10万ちょっとだった場合の還付金額」などを解説していきます。
目次
年間の医療費等の合計が10万円を超えない場合でも、条件によっては医療費控除を利用することができます。どんな条件があるのか説明していきます。
結論から言うと、次の2点の条件を「どちらも」満たす場合は、医療費などの総額が年間10万円以下でも医療費控除を利用することができます。
そもそも何故、一般に「医療費控除は医療費が10万をこえていないと使えない」といわれているのかといえば、医療費控除の控除額を計算する式が下記の通りになっているためです。
式を見てみてください。「医療費等の合計」が10万円以下の場合、控除額が0円になってしまうので、医療費控除が利用できないのです。
【年間の所得が200万を超える場合の控除額】
[医療費などの合計額 - 保険金などで補てんされる金額] - [10万]
ですが、年間所得が200万以下の場合は医療費控除の計算方法が異なります。下記のように、最後に引く金額が「10万」ではなく「所得金額の5%」になるのです。
このため、年間所得が200万以下の場合、医療費などの合計額(から保険金等を引いた金額)が10万円を超えていなくても「所得の5%」よりも多ければ医療費控除を利用できるのです。
ここで一点、注意したいポイントがあります。
「所得」とはいわゆる額面の年収などの「収入」ではなく、収入額から必要経費を差し引いた金額を指します。
会社員などのお給料についていえば、給与収入から「給与所得控除額」を引いた金額、つまり源泉徴収票に書いてある「給与所得控除後の金額」が「所得」にあたります。医療費控除の計算をするうえで間違えないようにしましょう。
収入が給与のみの場合、おおよそ年収290万以下であれば年間所得が200万以下になるでしょう。
(正確には、年収297万2,000円未満の場合、所得が200万円以下になります。)
所得金額が200万以下の場合、「前年1年の医療費等の合計から保険金等を引いた金額」が「所得の5%」よりも多ければ医療費控除を利用できます。
例えば所得が100万円だったとすると「所得の5%」は5万円ですから、この場合、医療費などの合計額から保険金等を引いた額が5万円を超えれば医療費控除を利用することができます。
所得が200万円を超えていて、医療費などの合計額が10万円に少しだけ届かなかった……という方も、医療費控除を諦めるのは少し早いかも知れません。以下のポイントに気を付けてもう一度計算してみることをおすすめします。
医療費控除の対象となるのは、医師に支払った治療費だけではありません。
通院のための交通費やメガネ、おむつなど医師の指示で治療のために必要とされた医療器具などの費用も控除の対象とすることが出来ます。
医療費控除の対象となるもの、ならないものについての詳細は以下の記事で解説しています。
医療費控除は本人だけでなく、家族のために支払った医療費などもあわせて控除出来ます。ここでいう家族とは「生計を一にする配偶者や家族」のことを指します。
例えば以下のケースも対象です。
下記の記事・動画で様々なケースについて解説しておりますので、ぜひご覧ください。
医療費控除の計算では、医療保険などで補てんされた金額を医療費の合計から差し引く必要があります。
ただし、個々の治療で支払った金額に対して、受け取った保険金などが上回った場合は、他の治療で支払った費用から差し引く必要はありません。
医療費控除の際は、支払った医療費などの合計額から出産育児一時金や入院給付金などで補てんされる金額を差し引く必要があります。
しかし健康保険の傷病手当金や出産手当金などは差し引く必要はありません。これらは治療費の補てんではなく収入の保障を目的として給付される給付金のためです。
例えば、がん保険の「がん診断給付金」も医療費を補てんするものではありませんので医療費から差し引く必要はありません。
上記の方法で集計してみても医療費等の合計金額が10万以下になるようであれば、セルフメディケーション税制を検討してみましょう。
風邪薬やロキソニンなどの医薬品(指定のOTC医薬品)の購入費や、予防接種・健康診断等の費用を合計して12,000円を超えるようなら、セルフメディケーション税制で控除を受けることが可能です。
おさらいになりますが、所得が200万円を下回る場合、「医療費など合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を引き、「所得金額の5%」を引いた残りの金額が「医療費控除の控除額」になります。
ただし、ここで勘違いしてはいけないのが、「控除額」=「医療費控除によって手元に戻ってくるお金」ではないことです。
医療費控除によって戻ってくる税金(還付額)の求め方は下記のとおりです。
この計算式に出てくる「所得税率」は所得の金額によって異なります。所得が200万以下の方の場合、所得税率は以下のいずれかになるでしょう。
また、確定申告で医療費控除を利用すると翌年の住民税も減額されます。住民税率は10%なので節税額は下記のとおりです。
【医療費控除による住民税の節税額】
[医療費控除の控除額] × [住民税率10%]
給与収入(年収)、年金収入(月額)10万円ごとの、医療費控除の還付額・減税額の早見表がありますのでご覧ください。
それでは実際の医療費控除の還付額をモデルケースを元に計算してみましょう。20代独身・会社員のAさんの例を挙げて解説していきます。Aさんの年収や医療費の合計は以下の通りです。
Aさんの「所得」は年間の給与収入240万から給与所得控除(この場合80万)をひいて160万です。「年間所得が200万以下」という条件に当てはまりますから、Aさんの場合は医療費等の合計が10万以下でも所得の5%を超えていれば医療費控除を利用できます。
まずは医療費控除の控除額を求めましょう。所得が200万以下の場合、医療費控除の控除額は「医療費の合計」から「保険金などの金額」と「所得×5%」を引いた金額でしたね。
Aさんの場合、「医療費の合計」、「保険金などの金額」、「所得×5%」はそれぞれ以下の通りです。
控除額の計算式に当てはめると、Aさんの医療費控除の控除額は下記のとおり、1万5千円になります。
続いて、今計算した控除額に所得税率をかけて、実際に税金がいくら戻ってくるのかを計算します。Aさんの所得は160万。所得が195万以下のなので、所得税率は5%です。
また、翌年から住民税は控除額の10%安くなりますから、住民税の節税額は以下の通りです。
[医療費控除の控除額 1万5千円] × [住民税率 10%]
=[節税額 1500円]
このように、Aさんのケースでは、確定申告により750円が還付され、翌年の住民税の支払額が1500円減額され、合計で2250円の節税となります。
ここまで、医療費が10万以下の方の還付金額について、計算方法やシミュレーションをお見せしましたが、いろいろと計算するのは少し面倒ですよね。
還付金の金額を自動で計算できるツールを用意しましたので、「自分の場合はいくら還付金が戻るのか」をすぐに確認したい方はご利用ください。
年間所得が200万をこえているものの医療費が10万円を少ししか超えない場合、医療費控除でどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか? 金額をシミュレーションしてみましょう。
20代独身のBさんの年収や医療費が次の通りだったとしましょう。
Bさんの所得は200万をこえているので、医療費控除の控除額は下記の式で求めます。Bさんの医療費は11万ですから、11万-10万で、控除額は1万円です。
また、Bさんの所得は276万円。195万円超330万円以下なので所得税率は10%です。このため還付額は下記の通りです。
また、翌年から住民税は控除額の10%安くなりますから、節税額は以下の通りです。
[医療費控除の控除額 1万円] × [住民税率 10%]
=[節税額 1000円]
医療費が10万とちょっとのBさんのケースでは、確定申告により1000円が還付され、翌年の住民税の支払額が1000円減額され、合計で2000円の節税となります。
先ほどのシミュレーション結果を見て、会社員の方などは「千円二千円のために確定申告をするのは面倒くさいな」と思われるかもしれません。
確かに、「確定申告を一度もしたことがない」という方の場合、手書きで確定申告書を作成するとなるといろいろと調べ物をしたり計算方法につまづいて何時間もかかったりして、「時給換算でむしろ損してない……?」と思ってしまいそうですよね。
ただ、最近はスマホで比較的簡単に確定申告ができますし、面倒な計算の大部分はオンラインでの自動計算が可能となりました。
数千円でもスマホでさっと確定申告をして戻ってくるならいい事ですし、もし確定申告をしたことがないという方であれば、確定申告の手順はどのみち知っておいて損はありません。
ここまで、医療費が10万ちょっとでも医療費控除を受ける意味はあるとお伝えしました。
ただし! 会社員の方などで副業をされている場合は注意が必要です。
会社員の皆さんの場合、副業をしていても副業所得が20万以下なら確定申告は不要です。つまり、副業所得が0~20万ならその分の所得税を支払わなくていいのです。
ですがもし、医療費控除のために確定申告をするという事になったら、副業所得が20万以下でもその金額を申告をしなくてはいけません。つまり所得税の支払いが増えるという事です。
医療費控除による控除額が少なく副業所得の金額が大きい場合、確定申告をすることでかえって損をする可能性もあります。
ということで、医療費が10万ちょっとで副業所得が20万以下の方は事前に還付金額(あるいは追加徴収金額)のシミュレーションをしておいた方がいいでしょう。
医療費の合計が10万以下の場合でも、医療費控除の手続き方法や必要書類に変更点はありません。
医療費控除の手続き方法は大まかに次の3種類に分けられます。
①の方法は税金の計算も自分でするので難しく、ミスもしやすいです。②③では、必要事項の入力をすれば税金の細かい計算は自動で行われるので比較的簡単だと言えます。
②③の違いは、②では書類をプリントアウトして税務署に直接、あるいは郵送で提出しないといけないのに対して、③の方法なら申告の手続きを全てオンラインで完結できます。
ただし③の方法を行うにはマイナンバーカードが必須です。また、③の方法をとる場合、マイナポータル連携という機能を使って医療費通知に載っている情報を自動で取得する方法と、医療費の領収書などを見ながら手入力する方法があります。
詳しいやり方については以下の記事・動画にて解説しておりますので、ぜひご確認ください。
ここまでお伝えしたように所得金額が200万円を下回る場合は、医療費などの合計額が10万円以下でも医療費控除をうけられるケースがあります。
控除により住民税の計算の基礎となる所得から控除することができるので、翌年の住民税の支払額も減額となります。
この記事を簡単にまとめていきます。
最後に、この記事を読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。よかったらぜひ、併せてご活用ください。
【関連記事】