2024年衆院選 比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数
2024年10月27日(日)に行われた2024年衆院選の比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数の一覧です。[続きを読む]
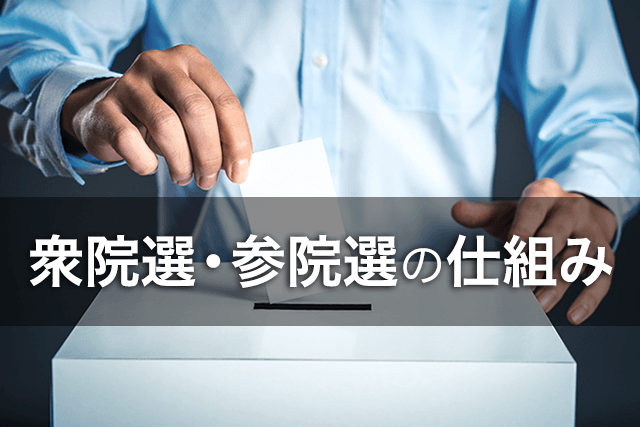
現在の日本では、衆議院選挙・参議院選挙のどちらも、次の2つを混合した仕組みがとられています。
ただ、衆議院選挙と参議院選挙では細かい点が異なりますので、それぞれ詳しく解説します。
目次
はじめに、衆議院と参議院の選挙について基礎から簡単におさらいしておきます。
日本の国会は衆議院と参議院の二院制をとっており、どちらも国民による選挙によって国会議員を選びます。
日本国憲法では、衆議院の任期は4年とされており、選挙で全員を入れ替えます。任期途中でも途中解散があります。
衆議院の定数は、別途、公職選挙法によって決められ、法律改正によって変動します。2026年の衆議院選挙では、衆議院の定数は465人です。
日本国憲法では、参議院の任期は6年で、3年ごとに選挙で半数を入れ替えます。衆議院のように任期途中での途中解散はありません。
参議院の定数も、別途、公職選挙法によって決められ、法律改正によって変動します。2018年改正公職選挙法成立により、定数は従来の242人から6人増えて248人になりました。
2019年の参議院選挙では、定数の半分の124人が選挙の対象になりました。ただし、2019年の参院選で増加するのは3人分だけですので、2019年時点では定数は245人です。
2022年・2025年の参議院選挙では、定数の半分の124人が選挙の対象になりますので、その後は、定数が248人となりました。
本章では、衆議院/参議院それぞれの仕組みを解説します。
説明にあたって、次のような各種選挙方式の用語が登場しますが、詳細については、3章で説明します。
用語説明を先にご覧になりたい方は、下記リンクから該当説明に飛ぶことができます。
衆議院選挙では次の2つの選挙方式があり、両方に対して別々の用紙で投票を行います(計2枚の投票用紙に記入します)。
2つを総称して「小選挙区比例代表並立制」と呼ばれます。
| ①小選挙区選挙 | ②比例代表選挙 | |
|---|---|---|
| 議席数 | 289議席※ | 176議席※ |
| 単位 | 小選挙区単位 (全国289選挙区※) |
ブロック単位/政党単位 (全国11ブロック※) |
| 記入方式 | 候補者名 | 政党名 |
| 当選決定方式 | 得票数順 | ドント式による拘束名簿式 |
※2026年衆院選時点
小選挙区選挙では、全国を約300近くの小選挙区に区切り、候補者はある1つの選挙区で立候補します。複数の小選挙区で立候補することはできません。
有権者は自分の小選挙区の候補者の中から1名のみ名前を記入します。他の小選挙区の候補者の名前を書くことはできません。
それぞれの小選挙区で最も得票数の多い候補者1名が当選します。ただし、有効投票総数の6分の1以上の得票が必要です。
比例代表選挙は全国を11ブロックに区切った政党単位であり、各政党は事前に当選順位が決められた候補者名簿を提出します。
| ブロック名 | 定員 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 北海道 |
| 東北 | 12 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 北関東 | 19 | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
| 南関東 | 23 | 千葉、神奈川、山梨 |
| 東京 | 19 | 東京 |
| 北陸信越 | 10 | 新潟、富山、石川、福井、長野 |
| 東海 | 21 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
| 近畿 | 28 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国 | 10 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国 | 6 | 香川、徳島、愛媛、高知 |
| 九州 | 20 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
小選挙区選挙の候補者が比例代表選挙に重複して立候補することが認められていますので、小選挙区選挙で落選しても比例代表選挙で復活当選することがあります。
有権者は政党名1つを記入します。
衆議員選挙では、「ドント式による拘束名簿式」という方式がとられており、各政党ごとに投票された割合で議席が割り当てられ、その政党の候補者名簿であらかじめ決められ順番に当選となります。
参議院選挙では次の2つの選挙方式があり、両方に対して別々の用紙で投票を行います(計2枚の投票用紙に記入します)。
| ①選挙区選挙 | ②比例代表選挙 | |
|---|---|---|
| 議席数 | 74議席※ | 50議席※ |
| 単位 | 各都道府県単位 (全国45区※) |
全国単位/政党単位 (全国1ブロック※) |
| 記入方式 | 候補者名 | 政党名または候補者名 |
| 当選決定方式 | 得票数順 | ドント式による拘束名簿式と 非拘束名簿式の混合 |
※2025年参院選時点、鳥取・島根と徳島・高知は隣接県との合区
選挙区選挙では、各都道府県ごとに区切り、候補者はある1つの選挙区で立候補します。複数の選挙区で立候補することはできません。
有権者は自分の選挙区の候補者の中から1名のみ名前を記入します。他の選挙区の候補者の名前を書くことはできません。
それぞれの選挙区での議席は人口に応じて決定されます。人口の多い都道府県では議席数が多く、人口の少ない都道府県では議席数が少なくなります。
2019年参院選では、埼玉県のみ1人定数が増え、次のようになりました。
| 選挙区 | 数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 2人区(1人改選) | 32 | 下記以外 |
| 4人区(2人改選) | 4 | 茨城県、静岡県、京都府、広島県 |
| 6人区(3人改選) | 4 | 北海道、千葉県、兵庫県、福岡県 |
| 8人区(4人改選) | 3 | 埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府 |
| 12人区(6人改選) | 1 | 東京都 |
【参考】2016年参院選では選挙区定数の10増(北海道・東京・愛知・兵庫・福岡各2人)10減(宮城・新潟・長野各2人、鳥取・島根と徳島・高知を合区し各2人)が行われ、各都道府県の定数が大幅に変更されました。
比例代表選挙は全国単位/政党単位であり、各政党は事前に候補者名簿を提出します。
選挙区選挙の候補者が比例代表選挙にも重複して立候補することは認められていません。
従来、参議員選挙では、「ドント式による非拘束名簿式」という方式がとられていましたが、2019年の参院選から、(1)拘束名簿式と(2)非拘束名簿式の両方が併用されることになりました。2種類の候補者名簿が存在することになります。
2019年参院選から、「特定枠制度」が新たに導入されました。その政党内で優先的に当選させたい候補者を特定枠として名簿に記載することで、名簿記載順に当選させることができます。
その他の候補者については、非拘束名簿式により、各政党ごとに投票された割合で議席が割り当てられ、その政党内では個人名で得票数の多い候補者から順番に当選となります。
有権者は、政党名1つまたは各党の名簿に記載されている候補者名1名を記入します。
政党名を記入した場合はその政党の総得票数がプラス1となります。
非拘束名簿式に記入されている候補者名を記入した場合は、その候補者に1票が入ると同時にその候補者が所属する政党の総得票数もプラス1となります。
拘束名簿式(特定枠)に記入されている候補者については、個人としての選挙運動は認められておらず、その候補者名を記入した場合は、単純にその政党の総得票数がプラス1となります。
拘束名簿式(特定枠)に記載されている候補者が優先して当選し、次に、非拘束名簿式に記載されている候補者が当選します。
たとえば、政党Xの拘束名簿にA,Bの2人、非拘束名簿にC,D,E,Fの4人が記載されていて、当選者枠が4人だった場合、まずは、拘束名簿の2人A,Bが優先して当選し、その次に、非拘束名簿の中で個人名で投票数の多いD,Fが当選します(下記表参照)。
| 名簿 | 氏名 | 個人名 投票数 |
当選順位 |
|---|---|---|---|
| 拘束名簿 | A氏 | - | 1 |
| B氏 | - | 2 | |
| 非拘束名簿 | C氏 | 100 | (落選) |
| D氏 | 500 | 3 | |
| E氏 | 200 | (落選) | |
| F氏 | 300 | 4 |
拘束名簿式(特定枠)の候補者を擁立するかどうかや、その人数は各政党が自由に決めることができます。
2022年の参院選では、自由民主党、れいわ新選組、ごぼうの党が特定枠を設定し、そのうち、自由民主党で2名、れいわ新選組で1名の、合計3名が当選しました。
特定枠の候補者は、個人としての選挙活動は認められていません。選挙事務所を開設したり、選挙カーを利用して、個人名を宣伝することはできません。ただし、政党名での活動はできます。
衆院選と参院選のどちらも仕組みが似ていますが、細かい違いをまとめておきます。
| 衆議院選挙 | 参議院選挙 | ||
|---|---|---|---|
| ①選挙区制 | 選挙区 | 全国289の小選挙区※ | 全国45の選挙区※ |
| 記入方法 | 候補者名 | 候補者名 | |
| 当選決定方式 | 最多得票者1名 | 得票順に複数名 | |
| ②比例代表制 | ブロック | 全国11ブロック※ | 全国1ブロック※ |
| 記入方法 | 政党名 | 政党名または候補者名 | |
| 当選決定方式 | ドント式による拘束名簿式 (名簿記載順に当選) |
ドント式による ・拘束名簿式(名簿記載順に当選) ・非拘束名簿式(政党内での得票数順に当選) の混合 |
|
| 重複立候補 | 認められている (復活当選あり) |
認められていない (復活当選なし) |
|
※2026年衆院選時点、2025年参院選時点
比例代表制はやや仕組みが複雑なため、詳しく解説します。
ドント方式とは比例代表選挙における議席配分の計算方法の一つで、現在、日本の衆議院議員比例代表選挙、参議院議員比例代表選挙で採用されています。
文章で説明すると複雑ですので、具体的を示します。
【条件】
・対象議席数:6議席
・対象政党:政党A、政党B、政党C、政党D
・各党の得票数:政党A1,200票、政党B900票、政党C600票、政党D300票
| 政党A | 政党B | 政党C | 政党D | |
|---|---|---|---|---|
| 得票数÷1 | 1,200 (1) |
900 (2) |
600 (3) |
300 |
| 得票数÷2 | 600 (3) |
450 (5) |
300 | 150 |
| 得票数÷3 | 400 (6) |
300 | 200 | 100 |
| 議席数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
【決定方法】
手順① 各政党の得票数をそれぞれ1、2、3、・・・で割った表を作成します。
手順② 上記の表の値をすべて比較して、値が大きい順に6つ選び(赤色の数字)、縦の列を見て選ばれた欄の数が各政党の議席数になります(政党A3議席、政党B2議席、政党C1議席、政党D議席なし)。
非拘束名簿式とは、当選する順番を決めずに、有権者の投票数によって当選順番を決める方法です。
参議院議員選挙の比例代表選挙では、政党名または候補者名を記入します。政党名の得票数と候補者名の得票数の合計がその政党の総得票数となり、その総得票数に応じてドント方式で各政党の議席数が決まります。そして、政党内では、各候補者の得票数に応じて当選が決まります。有権者は政党を選ぶだけでなく、その政党内での候補者も指定することができます。
具体例で確認します。
【条件】
・対象議席数:3議席
・対象政党:政党A、政党B
・各党の総得票数:政党A450票、政党B300票
【各政党の候補者名簿】
| 政党A | 政党B |
|---|---|
| C氏 | F氏 |
| D氏 | G氏 |
| E氏 | H氏 |
【各政党の得票数】
| 政党A | 200票 | 政党B | 50票 |
| C氏(当選) | 150票 | F氏(当選) | 130票 |
| D氏(当選) | 70票 | G氏 | 80票 |
| E氏 | 30票 | H氏 | 40票 |
| 政党Aの総得票数 | 450票 | 政党Bの総得票数 | 300票 |
| 政党A | 政党B | |
|---|---|---|
| 得票数÷1 | 450 (1) |
300 (2) |
| 得票数÷2 | 225 (3) |
150 |
| 議席数 | 2 | 1 |
【決定方法】
手順① 各政党の総得票数を計算
手順② ドント方式により、政党Aは2議席、政党Bは1議席を獲得
手順③ 各政党内で候補者の得票数の多いほうから当選
D氏はG氏より得票数が少ないですが、所属する政党Aの総得票数が多いため当選となります。
拘束名簿式とは、名簿で当選する順番が各政党によって決められている方式です。簡単にいえば、当選させたい順に書いた名簿の上から順番に当選していきます。
衆議院議員選挙の比例代表選挙では、政党名のみを記入し、政党名の得票数に応じてドント式で議席数が決まります。有権者は政党を選ぶことはできますが、当選者は各政党に委ねられます。
具体例で確認します。
【条件】
・政党Aは、選挙区選挙で4人を選出し2人が当選、比例代表選挙で5人を選出し2議席を確保
・選挙区と比例代表で重複する候補者がいる
・選挙区ではA氏とB氏が当選
【選挙区の候補者と結果】
| 選挙区 | 候補者 | 当落 | 惜敗率※ |
|---|---|---|---|
| 第1選挙区 | A氏 | 当選 | - |
| 第2選挙区 | B氏 | 当選 | - |
| 第3選挙区 | C氏 | 落選 | 80% |
| 第4選挙区 | D氏 | 落選 | 60% |
惜敗率:選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合のこと。たとえば、当選者が100票で落選者が80票なら、惜敗率は80%。
【比例代表の候補者名簿】
| 届出順位 | 候補者 | 選出要件 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 1位 | E氏 | 比例代表単独 | 当選 |
| 2位 | B氏 | 小選挙区当選 | - |
| C氏 | 小選挙区落選 惜敗率80% | 当選 | |
| D氏 | 小選挙区当選 惜敗率60% | 落選 | |
| 3位 | F氏 | 比例代表単独 | 落選 |
選挙区と比例代表で重複する候補者がいる場合、それらの候補者の名簿順位を同一にすることができます。このときは、「惜敗率」を使って同一順位内の各候補者の順位を決定します。
手順① 届出順位1位のE氏が当選
手順② 届出順位2位は3名いるが、選挙区で当選のB氏は除外。C氏とD氏では選挙区での惜敗率の高いC氏が当選。
仮にE氏がまったく人気のない候補者だったとしても、比例代表の名簿でトップに書いてあり、その政党が議席を獲得できれば当選します。
実例として、過去の比例代表選挙における、各政党の得票数と獲得議席の関係を作成していますので、下記のリンクからご覧ください。(大きな表が含まれています。)
2025年参議院選挙の給付金・税金・経済政策関連の政策・公約(マニフェスト)を比較しています。