退職金にかかる税金の計算方法|確定申告は必要?
退職金の受け取り方法と、それによってかかる税金(所得税・住民税)の計算方法や、確定申告・年末調整が必要かどうかについ…[続きを読む]
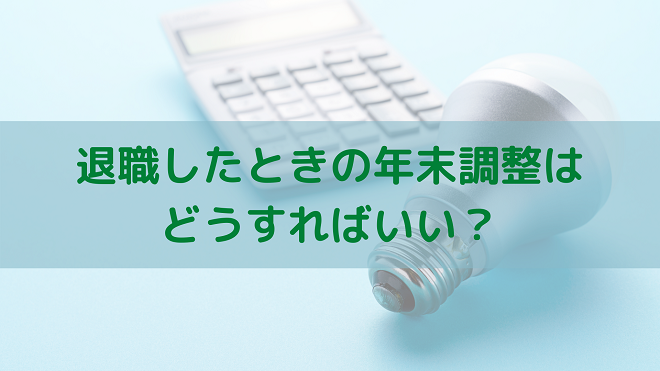
会社を退職した年の年末調整では、注意すべき点がいくつかあります。特に11月・12月に退職したときは、年末調整がやや複雑になります。
この記事では、会社を退職した場合の年末調整手続きについてわかりやすく解説します。
目次
1年を通して同じ会社で勤務している場合は、会社の指示通りに年末調整の書類を提出するだけで終了です。しかし、年の途中で退職そして転職した場合は、手続きが異なります。
退職・転職した場合の年末調整では
で扱いが異なります。
再就職した会社で年末調整を行うことになります。その際に退職した会社から源泉徴収票をもらい、再就職先の会社に提出する必要があります。
また、退職金については年末調整の対象ではありません。退職金は支給時に税金が差し引かれて、それだけで納税が完了するので確定申告の必要もありません。
「退職金と税金」については以下の記事も併せてご覧ください。
年末時点で再就職していない(無職の)場合、自分で確定申告を行わなければなりません。
通常、退職した会社では退職者の年末調整をしません。
ただし、例外的に次の条件に該当する退職者へは退職時に年末調整を行うことができます。
なお、この場合についても退職金の年末調整・確定申告は原則不要になります。
①②それぞれのケースについて、さらに詳しく解説していきます。
年の途中で退職して年内に再就職した場合は、新しい会社で年末調整を行うことになります。前の会社の収入と新しい会社の収入を合算し税額を確定させます。
ここで必要になる書類が、退職した会社から発行される「給与所得の源泉徴収票」です。
再就職した会社で年末調整を行うために、前の会社の収入金額や源泉所得税の金額が記載された源泉徴収票が必要になります。
退職する会社では源泉徴収票を必ずもらいましょう。退職後、年内に再就職する場合でも、しない場合でも必要になる重要な書類です。
所得税法では、退職者に対する源泉徴収票の発行は退職から1ヵ月以内に交付しなければならないと定められています。
しかし、しばしば退職した会社から源泉徴収票を発行してもらえないケースがあります。
源泉徴収票がないと再就職した会社で年末調整を行うことができず、再就職した会社に迷惑をかけることになります。
そのため、遅くても年末調整の書類収集が始まる10月までには発行してもらえるようにしましょう。
会社には源泉徴収票の発行義務があるため、まずは会社に問い合わせてみましょう。
どうしても源泉徴収票の発行に応じてもらえない場合は、所轄の税務署に相談し「源泉徴収票不交付の届出」を税務署に提出する方法があります。
この届出を行うことで、源泉徴収票の発行を行わない会社へ行政指導が入ります。
届出には、1月から退職月までの給料の金額や源泉徴収税額の金額などを記入しなければならないため、毎月の給料明細は大切に保管しましょう。
退職した会社から発行された源泉徴収票を紛失した場合は、退職した会社に再発行を依頼する必要があります。
再発行してから実際に手元に届くまで早くて数日、遅くても3週間ほど必要になるでしょう。退職した会社に源泉徴収票の再発行を依頼するのは心情的に気が引けてしまうことが多いので、退職時に交付された源泉徴収票は紛失しないように心がけましょう。
11月に退職し12月に再就職した場合、退職した会社からの源泉徴収票が間に合わないケースがあります。
特に、月末締め翌月払いの会社では、11月末に退職しても、11月分の給与が12月に支払われ、それから源泉徴収票の作成になりますので、通常、再就職先での年末調整に間に合いません。
この場合は、再就職した会社で年末調整を行うことができないため、翌年に退職した会社の源泉徴収票と新しい会社の源泉徴収票を合算して自分で確定申告する必要があります。
また、12月に再就職した会社の給料の支払いが翌月払いの場合は、初めての給料が翌年1月に発生するため年末調整が行われないことがあります。この場合についても自分で確定申告を行わなければなりません。
ただし、年末調整は翌年1月末までに終えればいいことになっているため、1月に支給する給料がある場合については年末調整を行う会社もあるので、入社時に確認するといいでしょう。
12月のどのタイミングで退職するかによって異なります。
12月31日に退職するのであれば、その年の最後の給料が支払われてから退職することになりますし、再就職先の会社で給料をもらうのは翌年1月からですので、退職した会社で年末調整を行います。
たとえば、給料日は毎月25日だが、その前の12月10日に退職した場合、まだ12月の給料が支払われる前の退職になりますので、通常、退職した会社では年末調整を行いません。
ただし、会社側で年末調整を行ってはいけないという決まりはありませんので、再就職先で12月に給料をもらう予定がなければ、退職した会社にお願いすれば年末調整を行ってもらえることもあります。
ここはケースバイケースですので、退職時に会社に相談すると良いでしょう。
年の途中で退職後、年内に再就職をせず無職の場合、または個人事業主・フリーランスになった場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、同じ給料を1年間もらい続けた場合の所得税額を基準に算定されています。
年の途中で退職すると1年間の合計収入が少なくなるため、天引きされ過ぎている状況になり、確定申告をすることで過払い分の源泉所得税の還付を受けることができます。
収入が退職した会社の給料のみの場合、確定申告の手続きは複雑ではありません。ここでは「年内に再就職しなかった場合の確定申告」を簡単にご紹介します。
確定申告の期間は、原則的に毎年2月16日~3月15日になります。正確な日付は曜日の関係で毎年異なります。
ただし、還付を受ける申告(還付申告)の場合は2月16日以前でも確定申告書の提出が可能です。
確定申告書の提出先は、住所地を管轄する税務署になります。提出方法は、税務署に直接提出する方法と郵送で提出する方法、インターネット(e-Tax)を利用して提出する方法があります。
退職し、給料以外の収入が無い場合には次の書類が必要になります。
退職した会社から発行される源泉徴収票です。忘れずに発行してもらい、紛失しないように確定申告まで保管してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
生命保険料や個人年金、地震保険料の支払いがある場合、保険料控除証明書を添付することで所得税額を減額することができます。各保険会社から10月ぐらいに郵送されてきますので、紛失しないように保管しておきましょう。
退職後に国民年金に加入している場合、控除証明書を添付することで所得税額を減額することができます。
退職後に国民健康保険に切り替え、保険料の支払いがある場合は所得税額を減額することができます。他の保険料と異なり、控除証明書の添付は必要ありませんが、計算には支払った金額が分かるものが必要になります。領収書や口座引き落としが分かる通帳などの準備が必要です。
確定申告に必要な確定申告書用紙は、税務署で入手することができます。また、国税庁のサイトでもプリントアウトすることができます。
国税庁のe-Taxでオンラインでの確定申告書の作成も可能です。オンラインで確定申告書の提出をしない場合でも、入力した確定申告書をプリントアウトし税務署に提出することができます。
【参考】国税庁:確定申告書特集
退職して再就職しない場合、自分で確定申告が必要と述べましたが、例外として、12月の給料が支払われてから退職した場合は、退職した会社で年末調整を行います。この場合は、確定申告は不要です。
パート、アルバイトを退職した場合についても、通常の退職と同様に年末調整は行われません。
年内に他のパートやアルバイトを始めた場合は、前の勤務先の源泉徴収票を再就職先に提出し、合算して年末調整を行います。
ただし、年内にパートやアルバイトをする見込みがなく、年間で収入の合計が160万円以下の人は法令上、退職時に年末調整をすることが可能ですので、勤め先に相談してみると良いでしょう(とはいえ勤め先によっては年末調整を行いたい旨を伝えても拒否されてしまう可能性もあります)。
また、アルバイトを掛け持ちしており、2ヵ所以上から収入を得ている場合は1ヵ所からの収入が年末調整されている場合であっても確定申告が必要です。各アルバイト先から源泉徴収票をもらい、確定申告で合算して所得税の計算を行わなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
退職したときの年末調整については、
となります。
ただし、退職が11月、12月の場合は、退職するタイミングによって、対応が異なることがありますので、ご注意ください。