年末調整で受けられる控除・受けられない控除の一覧
年末調整で受けられる控除と受けられない控除をまとめました。年末調整で受けられない控除は確定申告が必要です。[続きを読む]
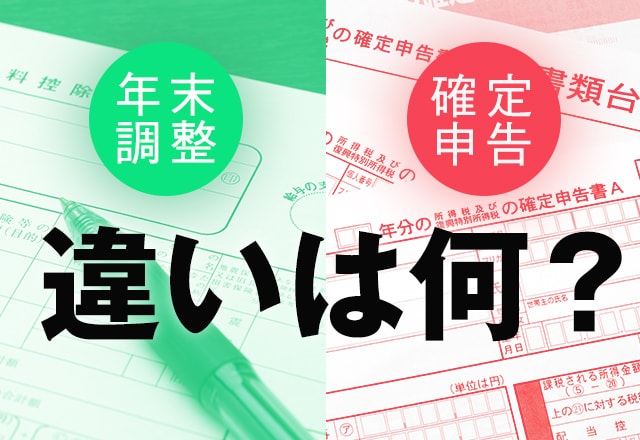
会社勤めの方は通常、勤務先で年末調整を行うことで所得税と住民税の金額が確定します。
確定申告をしない人のほうが多いのではないでしょうか?
しかし、会社員の方の中には確定申告をすべき人、または、した方がお得なケースもあるのです。
この記事では年末調整と確定申告の違いと、会社員でも確定申告が必要になるケースについて解説します。
年末調整も確定申告も、ご自身が1年間で稼いだお金にかかる税金(所得税)を正しく納め、清算するために行うものです。やっていることはどちらもほとんど同じですが、次のようにいくつかの違いもあります。
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 会社員・パート・バイト | 主に個人事業主 |
| 時期 | 年末 10月~12月くらい |
翌年2月~3月 |
| 書類の提出先 | 会社の担当部署 | 税務署 |
| 所得控除 | 配偶者控除 扶養控除 保険料控除 など一部 |
全部 |
| 住宅ローン控除 | 2年目からOK | 1年目は確定申告 |
それではここからは、年末調整と確定申告がそれぞれどんなものなのか、詳しくはどんな違いがあるのか確認していきましょう。
年末調整とは、会社員の1年間の所得税(稼ぎにかかる税金)の金額を確定させるための手続きです。
会社員の皆さんの場合、毎月の給与から所得税が天引きされていますが、ここで天引きされている金額は概算で、正確な金額ではありません。
年末調整で配偶者控除や扶養控除、保険料控除などの各種控除の金額を書類に記入し、勤務先に提出することで、はじめて正確な1年間の所得税額が確定します。
その確定した所得税額と、毎月天引きされていた金額(源泉所得税額)との差額を調整する、というのが年末調整の一連の流れです。
年末調整の対象者は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが前提となります。具体的に対象となるのは次のケースです。
要するに、年末時点で会社勤めをしている方は基本的に年末調整の対象となるということです。ただし一部例外もあるので、それについては後述します。
また、少し特殊なケースですが、年末ではなく年の途中に年末調整を行わなければならない人もいます。
上記いずれかのケースに該当する方は、年の途中時点で年末調整が行われます。逆に言えば年の中途で退職した人で上記に該当しない人は、年末調整の対象に含まれないこととなります。
会社員でも、以下に該当する人は年末調整の対象にはなりません。
また、上記以外でも、2か所以上の会社から給与を受け取っている方は注意が必要です。
その場合、メインの勤務先では扶養控除申告書を提出のうえ年末調整を行うこととなり、もう一方の勤務先では年末調整を行わないこととなります。
所得税の確定申告とは、個人が納税すべき所得税額を税務署に申告する手続きのことをいいます。
確定申告では給与所得以外の、事業所得や不動産所得等についても合わせて計算を行い、所得税額を確定させます。
確定申告は主に個人事業者や給与収入以外の収入がある人が行うものです。普通の会社員は年末調整で所得税額が確定するため、確定申告をする必要はありません。
ただし、会社員でも次のように年末調整の対象外の方、会社で年末調整を受けなかった方は自分で確定申告をする必要があります。
さらに、後述しますが「本業の会社以外に収入がある場合」など、年末調整と確定申告の両方が必要になるケースもあります。
ここまで年末調整と確定申告の概要を簡単に説明してきましたが、それぞれの相違点を表で整理しておきましょう。
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 時期 | 10月~12月頃 | 翌年2月16日~3月15日 |
| 書類の提出先 | 勤務先の会社 | 所轄の税務署 |
| 対象となる所得 | 給与所得 | 給与所得 事業所得 不動産所得等 (全10種類の所得) |
| 控除の種類 | 基礎控除 配偶者控除/配偶者特別控除 扶養控除/特定親族特別控除 障害者控除 ひとり親控除/寡婦控除 勤労学生控除 生命保険料控除 地震保険料控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 住宅借入金等特別控除 |
(左記以外に) 雑損控除 医療費控除 寄附金控除 特定支出控除 |
上の表を見ると、年末調整よりも確定申告の方が控除の種類が多いことが分かります。利用できる控除が多ければ多いほど税金は安くなりますのでご自分に適用できる控除はもれなく申請する必要があります。
ほとんどの所得控除は年末調整で申請できますが、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、特定支出控除は確定申告でしか申請ができないので、これらの控除を受けられる方は年末調整後に確定申告を行いましょう。
繰り返しになりますが、会社員の方でも年末調整を受けられなかった場合は確定申告が必要です。
また、年末調整を受けた人でも、次のようなケースでは確定申告が必要です。
また、多少特殊なケースとなりますが、以下に該当する方も確定申告を行う必要があります。
次のいずれかのケースに該当する方は、確定申告を行う必要があります。
上記のケースは、いずれも前職の収入について年末調整が行われていません。したがって前職の収入について、自分で確定申告を行わなければなりません。
年末調整で控除できるものをうっかり忘れてしまった場合、確定申告をすることで還付を受けることができます。例えば次のようなケースです。
生命保険料控除や住宅ローン控除は、証明書を紛失してしまって年末調整に間に合わなかったり、うっかり記入漏れしてしまうこともあるかと思います。
また、その年中に結婚したり、両親に仕送りをしているのに扶養家族欄に書き忘れてしまうことも考えられます。
このようなケースでは、自身で確定申告を行うことで、それらの控除を受けることが可能です。
特定支出控除とは、簡単に言えば会社員に認められた経費です。会社員が次の支出をした場合、確定申告により一定金額を控除することができます。
【特定支出の内容】
適用できる金額に要件があったり、会社の証明が必要だったりと一定のハードルはありますが、対象となる人は活用すべき制度です。
勤務先の何らかの都合によって、または自分の責任等により、年末調整すべき人が年末調整をしなかった場合、確定申告をしても良いのでしょうか?
年末調整をすることは会社側の義務であり、年末調整をしなくても労働者側に罰則の規定はありません。
年末調整で全て済ませることが原則ではありますが、年末調整できなかった場合には自分で期日までに確定申告をすればあなた自身に問題は生じません。
最後に、もう一度、年末調整と確定申告の違いについて、簡単にまとめます。
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 誰が | 勤務先 (会社員は書類を記入) |
自分で |
| いつ | 10月~12月頃 | 翌年2月16日~3月15日 |
| どこで | 勤務先の会社 | 所轄の税務署 |
| 対象の収入 | 給与収入 | すべての収入 |
| 控除 | 扶養控除 配偶者控除 生命保険料控除 など ※漏れたら確定申告でも可能 |
左記に加えて 雑損控除 医療費控除 寄附金控除 特定支出控除 ※確定申告でのみ可能 |