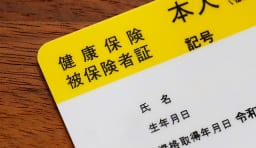マイナ保険証で医療費は高くなる?安くなる?

2023年4月1日以降、従来の健康保険証を利用した場合、受診料がさらに6円値上げされます。
マイナ保険証(マイナンバーカードを利用した健康保険証)が、いよいよ2024年秋に義務化されます。
そこで気になるのが、医療費です。マイナ保険証を利用すると、従来の健康保険証より、高くなるとか、逆に、安くなるとか、いろいろなことが言われていますが、本当のところはどうなのでしょうか?
いろいろな情報があって混乱しがちですので、わかりやすく整理してみました。
目次
1.マイナ保険証のほうが医療費が安い(2022年10月から)
結論からいってしまうと、2022年10月からは、マイナ保険証を利用して病院にかかったほうが安くなりました。
マイナ保険証を利用しても、従来の健康保険証を利用しても、どちらも診療報酬が加算されるのですが、2022年10月に診療報酬が改定されて、次のようになりました。(一般的な、窓口負担3割の場合)
| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |
|---|---|---|
| 初診時 | 6円 | 12円 |
| 再診時 | (なし) | (なし) |
| 調剤薬局での利用 | 6ヶ月毎に3円 | 6ヶ月毎に9円 |
マイナ保険証だと、初診時には6円かかりますが、再診時にはかかりません。調剤薬局での利用は、6ヶ月毎に3円です。
一方、従来の健康保険証だと、初診時には12円かかりますが、再診時にはかかりません。調剤薬局での利用は、6ヶ月毎に9円です。
つまり、マイナ保険証を利用したほうが、初診時には6円安く、調剤薬局での利用も6ヶ月で6円安いことになります。そこまで大きな金額の差ではありませんが、初診で病院にたくさんかかる人だと、ちょっとお得になるかもしれませんね。
2023年4月から、従来の健康保険証が値上げ!
2023年4月以降、従来の健康保険証を使うと、初診時も再診時もさらに6円高くなります(一般的な、窓口負担3割の場合)。
初診時は12円⇒18円に、再診時は0円⇒6円にアップします。
| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |
|---|---|---|
| 初診時 | 6円 | 12円⇒18円 |
| 再診時 | (なし) | (なし)⇒6円 |
| 調剤薬局での利用 | 6ヶ月毎に3円 | 6ヶ月毎に9円 |
マイナ保険証の負担は変わりません。そのため、従来の健康保険証は、マイナ保険証よりも、初診時で12円、再診時で6円高くなります。
政府は、マイナンバーカードを普及させたく、強引な手段に出ているようです。
2.当初はマイナ保険証のほうが医療費が高かった
「あれ、マイナ保険証のほうが医療費が高い!って聞いたことがある」という人もいるでしょう。
実は、当初、マイナ保険証が導入されたときは、マイナ保険証のほうが医療費が高かったのです。
2022年4月の時点では、次のように、マイナ保険証を利用すると、従来の保険証を利用するよりも、費用が高くなっていました。
| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |
|---|---|---|
| 初診時 | 21円 | 9円 |
| 再診時 | 12円 | (なし) |
| 調剤薬局での利用 | 1ヶ月毎に9円 | 3ヶ月毎に3円 |
マイナ保険証だと、初診時には21円かかり、再診時には12円かかりました。調剤薬局での利用は、1ヶ月毎に9円です。
一方、従来の健康保険証だと、初診時には9円かかりますが、再診時にはかかりません。調剤薬局での利用は、3ヶ月毎に3円です。
つまり、マイナ保険証を利用すると、初診時も再診時も12円高く、調剤薬局での利用も1ヶ月単位で8円高かったのです。
なぜ、マイナ保険証のほうが医療費が高いかというと、マイナ保険証を利用するためには、病院や薬局で、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーなどを導入しなければなりません。それらの導入費用は、基本的には、それぞれの医療機関の負担になりますので、診療報酬をあげて、患者や利用者に負担させても良いことになったからです。
3.2022年10月、診療報酬を改定
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)を利用するメリットは、以下のようなものがあります。
- 医療機関同士で患者の情報を共有できるので、適切な診療をできる
- 自分の医療情報を閲覧できる
- 確定申告での医療費控除の記入が楽になる
でも、マイナ保険証を利用すると、医療費が高くなるのだったら、こういうメリットがあったとしても、あえて利用したい人なんてほとんどいませんよね。
国民からも、医療機関からも批判の声があがっていましたので、政府は、2022年10月に診療報酬を改定して、マイナ保険証を利用したほうが医療費が安くなるようにしました。
4.診療報酬の詳細
さきほどは、窓口3割負担の場合を例にあげましたが、もう少し詳しく説明しますと、実際には、診療報酬は点数で決められていまて、1点あたり10円が加算されます。
2022年4月時点では、次のような点数になっていました(カッコ内は3割負担の金額)。
| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |
|---|---|---|
| 初診時 | 7点 (21円) |
4点 (12円) |
| 再診時 | 3点 (9円) |
(なし) |
| 調剤薬局での利用 | 1ヶ月毎に3点 (9円) |
3ヶ月毎に1点 (3円) |
マイナ保険証だと、初診時には7点、ということは70円の加算で、3割負担なら21円になるのです。
それが、2022年10月から改定され、次のようになりました。
| マイナ保険証 | 従来の保険証 | |
|---|---|---|
| 初診時 | 2点 (6円) |
4点 (12円) |
| 再診時 | (なし) | (なし) |
| 調剤薬局での利用 | 6ヶ月毎に1点 (3円) |
6ヶ月毎に3点 (9円) |
これらの診療報酬の加算は、マイナ保険証に対応している医療機関(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関)では加算されますが、マイナ保険証に対応していない医療機関では加算されません。
つまり、従来の保険証を利用しても、マイナ保険証に対応している医療機関では加算されて医療費が高くなってしまうのです。医療費を少しでも安くしたければ、マイナ保険証に対応していない病院や薬局を選ぶ必要がありました。
しかし、政府は、2023年4月までに、すべての病院や診療所、薬局に対して、マイナ保険証に対応することを義務付けています※ので、どの病院・薬局にかかったとしても、以前より医療費は少しアップするようになるでしょう。
※2023年3月末までにマイナ保険証への対応が間に合わないケースが4万~5万件あることが報じられており、やむを得ず2023年4月までにマイナ保険証に対応できない医療機関については2023年9月末までの期限付きの経過措置を設けられています。
マイナ保険証と医療費に関するFAQ
マイナ保険証を利用すると医療費が高くなる?安くなる?どちらですか?
マイナ保険証をを利用すると、従来の健康保険証を利用するより、医療費が安くなります。
窓口3割負担の人の場合、マイナ保険証を利用したほうが、初診時には6円安く、調剤薬局での利用も6ヶ月で6円安くなります。
マイナ保険証を利用するとマイナポイントがたまる?
マイナ保険証を病院や薬局で利用してもマイナポイントはたまりません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録すると、7500円分のマイナポイントをもらえます。ただし、期限がありますので、ご注意ください。
マイナ保険証に対応していない医療機関にかかったほうがお得?
マイナ保険証対応のための機器導入費用の一部を利用者にも負担させるために、マイナ保険証に対応している病院や薬局では、診療報酬が加算されます。マイナ保険証に対応していない医療機関であれば、追加はありませんので、お得です。
ただ、マイナ保険証が義務化される予定ですので、マイナ保険証に対応しない医療機関はなくなってしまうでしょう。
終わりに
2023年4月から、紙の保険証を利用することで医療費の負担が増えてしまうことをお伝えしました。医療費負担が気になる方はマイナンバーカードの保険証利用登録を検討してはいかがでしょうか。
医療費に関する重要TOPIC
- 医療費控除は医療費10万円以下じゃ意味ないの? 10万円ちょっとの場合は?
- 高額な医療費を支払ったら確定申告すべき?|高額療養費と医療費控除
- 確定申告の医療費控除、保険金・入院給付金の申告漏れはバレる?
医療費保険も検討すべき?
医療費負担が気になる方の中には医療費保険に加入している方、加入を検討している方もいるでしょう。
医療費保険を含め、保険について気になることがある方には以下のサイトもおすすめです。匿名で質問、相談でき、複数の全国の保険のプロから具体的アドバイスを貰うことができます。