11月・12月に退職したときの年末調整
会社を11月・12月に退職したときは、年末調整がやや複雑になります。この記事では、会社を退職した場合の年末調整手続き…[続きを読む]
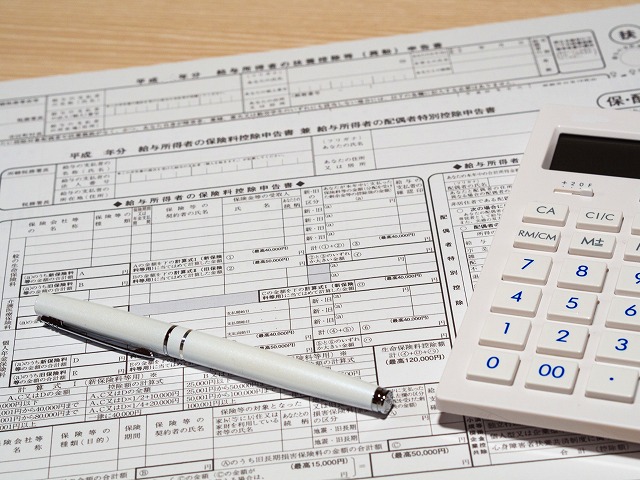
年末調整は、会社員や公務員など、基本的には、給料をもらって働く人のほとんどが対象者となりますが、一部、対象にならない人もいます。
年末調整の対象者になる人/対象者でない人を整理します。
目次
企業は従業員に、給料を支払う際に、所得税を差し引いて支払います。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収で差し引く所得税は仮の金額ですので、年末にその年のすべての給料を支払い終わるタイミングで、実際の金額を計算します。
そして、多く徴収しすぎていたら還付し、逆に足りなければ追加徴収します。
これが、「年末調整」ですので、対象者は、基本的には、給料をもらって働く人になります。
アルバイトやパートであっても、会社から給料をもらって働くことに、社員と変わりはありませんので、年末調整の対象者となりえます。
ただし、後で述べるように、複数の会社で働いている人は、メインの会社以外では年末調整の対象となりません。
給料をもらっていても、年末調整の対象となる人と対象とならない人がいます。
年末調整を受ける人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出する必要があります(すでに提出済みであればOK)。
この書類が提出されていないと、年末調整の対象者となりません。
いくつかのケースでの年末調整について書いておきます。
副業などで複数の会社に勤務している場合、年末調整は1つの会社のみで行います。
通常、メインの会社で年末調整を行い、それ以外の会社では年末調整は行いません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はメインの会社1社のみに提出できます。
退職者が年末調整の対象者となるのは、死亡・心身の障害等で、退職後、他社で給料をもらう予定がなく給与収入が確定している場合です。
または、12月に支払われる給与の支払後に退職した人です。
11月退職では、給料は11月に支払うか、12月に支払うかのどちらかですが、どちらにしても、上記の要件に該当しませんので、基本的には年末調整の対象となりません。
ただし、11月退職後、他社で働く予定がないことが確実にわかっているのであれば、年末調整を行うことも可能です。
12月退職では、退職日が給料の支払日よりも後であれば、年末調整の対象者となります。