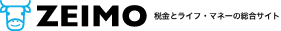休業手当は少なすぎて生活できない!給料の全額を保証してもらえる場合は?

新型コロナウイルスの影響を受け、自主休業をする店舗が相次いでいます。
店舗が自主休業をする際には、多くの場合、従業員に対して休業手当が支給されます。
しかし、実際に休業手当を受け取ってみて、その金額が思ったよりも少ないと驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
休業手当の計算方法は労働基準法で決まっていますが、その計算方法の性質上、休業手当の金額が月々の給料に比べてかなり少なくなってしまう場合があります。
このような場合、従業員としては生活に困ってしまうかもしれません。
会社都合の休業なのに、いつも受け取っている毎月の給料よりも少ない休業手当しかもらえないのは納得がいかないという方もいらっしゃるでしょう。
どうにかして会社に給料の全額を保証してもらうことはできないのでしょうか?
この記事では、
- 休業手当とは何か
- 休業手当の計算例
- 給料の全額を保証してもらえる場合はあるか
- 会社に休業手当などを支払ってもらえない場合の対処法
などについて詳しく解説します。
1. 休業手当とは?
休業手当とは、会社などが休業する場合に、使用者が労働者に対して支払うことが法律上義務付けられている手当をいいます。
休業手当については労働基準法26条に規定があります。
まずは休業手当を受け取ることができる要件などについて見ていきましょう。
1-1.「使用者」の責に帰すべき事由による休業の場合に受け取れる
労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には、労働者に対して休業手当を支給しなければならないものと定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、「会社など使用者側に責任がある場合」ということです。
休業手当は、労働者の最低限の生活を保障する観点から特に定められた手当です。
そのため、「使用者の責に帰すべき事由」は、通常の故意・過失よりも広い意味に解されています。
具体的には、不可抗力(天変地異など人の力ではどうにもできないこと)による休業以外は、すべて「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。
使用者が休業手当を支払う必要がない場合、つまり不可抗力による休業といえるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 休業の原因が事業の外部より発生した事故であること
- その事故が、事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
1-2.休業手当は平均賃金の6割以上
労働基準法26条により、休業手当の金額は「平均賃金の100分の60以上」とされています。
具体的な休業手当の計算方法については、次の項目で解説します。
1-3.休業手当の対象となるのは就業規則上の「所定労働日」
休業手当は1日単位で支給されますが、支給の対象となるのは就業規則上の「所定労働日」、つまり労働をしなければならない日についてのみです。
たとえば、土日祝が休日とされている会社であれば、休業手当は平日の日数分しか支給されません。
また、会社が定める夏季休暇や年末年始休暇などをまたぐ場合には、これらの日数についても休業手当の支給の対象外となります。
このように、1か月間のすべての日について休業手当が発生するわけではないことに注意しましょう。
2.休業手当の金額を計算してみよう
具体例に沿って実際に休業手当を計算してみて、休業手当としてどのくらいの金額がもらえるかのイメージを持っておきましょう。
なお、具体例では月給制を前提とします。
2-1.休業手当算定の基礎となる「平均賃金」とは?
休業手当は、「平均賃金」の6割以上と定められていますので、まずは「平均賃金」とは何なのかについて理解しておく必要があります。
平均賃金については、労働基準法12条1項に定義があります。
月給制の場合の平均賃金は、以下の計算式によって計算されます。
なお、上記でいう賃金には、基本給のみならず、時間外労働手当や深夜手当などの手当もすべて含まれます。
具体的な例を見ていきましょう。
- 2020年4月、5月、6月の3か月間休業
- 1月、2月、3月の賃金は、それぞれ28万円、33万円、30万円
この場合の平均賃金は、
=(28万円+33万円+30万円)÷(30日+31日+30日)
=91万円÷91日
=1万円
となります。
2-2.休業手当の計算式
1日当たりの休業手当の金額は、平均賃金の6割以上とされています。
そして、休業手当の支給対象となるのは、就業規則上の所定労働日のみです。
したがって、最低限の休業手当の計算式は以下のとおりとなります。
上記の例を引き続き考えてみましょう。
- 2020年4月、5月、6月の3か月間休業
- 1月、2月、3月の賃金は、それぞれ28万円、33万円、30万円
- 各月の所定労働日数は、それぞれ21日、18日、22日
上記の場合、平均賃金は1万円でした。
これと所定労働日数を用いて休業手当の総額を計算すると、以下のとおりとなります。
=1万円×60%×(21日+18日+22日)
=6000円×61日
=36万6000円
上記の例では、会社が休業することなくこれまでどおりのペースで労働を続けることができたと仮定した場合、この労働者は4月から6月までで約90万円の収入を手にすることができたと見込まれます。
しかし、4月から6月まで会社が休業した場合、この期間に受け取ることができる休業手当は36万6000円と、通常時の半分以下になってしまいました。
2-3.休業手当が思ったよりも少ない?
休業手当が予想よりも少ない金額になってしまうことが多いのは、以下の2つの理由によります。
- 休業手当は平均賃金の60%を支給すれば足りる
- 休業手当は所定労働日に対してのみ支給される
つまり、休業手当は通常の給与と比べて二重に減額されており、平均賃金と比べると非常に少ない金額になってしまうのです。
3.給料の全額を保証してもらうことはできないの?
たとえば新型コロナウイルスの影響などによりやむを得ず休業しているといっても、結局は会社都合による休業なのに、給料の全額を支払ってもらえないのは納得がいかないという方も多いのではないでしょうか。
実は、休業手当の金額を超えて、会社に対して給料の全額を支払うことを請求できる場合があります。
どのような場合に給料全額の請求が認められるかについて、詳しく見ていきましょう。
3-1.会社の休業にも民法536条2項の適用がある
労働者が会社に対して、会社の休業にもかかわらず給料の全額を請求できるのは、民法536条2項第1文が適用される場合です。
民法536条2項第1文には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない」と規定されています。
つまり、労働者が使用者(債権者)の責めに帰すべき事由によって労働を提供できなくなったときには、会社は労働者に対して給料全額の支払いを拒むことができません。
よって、休業が民法536条2項第1文に規定する「債権者の責めに帰すべき事由」による場合には、給料の全額を支払ってもらうことができます。
3-2.労働基準法26条と民法536条2項の関係は?
労働基準法26条と民法536条2項は、どちらも「会社の責めに帰すべき事由」による休業に適用される規定と読めます。
しかし、その意味する内容は互いに異なり、労働基準法26条に規定される「使用者の責に帰すべき事由」の方がより広く解されています。
先にも解説したとおり、労働基準法26条に規定する平均賃金は、労働者の最低限の生活を保障する趣旨から設けられていますので、使用者が免責されるのは不可抗力による休業の場合のみです。
一方、民法536条2項に規定する「債権者の責めに帰すべき事由」は、債権者の故意・過失を意味するものと解されています。
したがって、休業手当を受給できる要件は満たすけれども、給料全額を支払ってもらえる要件は満たさないということもあり得ます。
一方、より要件の厳しい民法536条2項に該当する場合には、労働基準法26条の要件も同時に満たすことになります。
たとえば、使用者が休業を回避する努力をせずに漫然と休業をし、労働者の労働機会を奪ったと認められる場合には、コロナの影響による休業であっても使用者の過失が認められる可能性が高いでしょう。
この場合、どちらが優先されるのでしょうか。
この点、休業手当について定めた労働基準法26条は、民法536条2項に基づく会社の責任を軽減する趣旨の規定ではありません。
よって、両方の規定の要件を満たす場合には、労働者は両方の請求権を行使することが可能とされています(最判昭和62年7月17日)。
したがって、民法536条2項の要件を満たす場合には、労働者は会社に対して給料全額の支払いを請求することが可能です。
3-3.休業中に労働者が副業などで収入を得ていた場合は?
民法536条2項第1文が適用され、給料の全額を支払ってもらえる場合であっても、労働者が副業収入などによって休業期間中に利益を得ていた場合には、その利益が受け取ることができる給料から控除されてしまいます(同項第2文)。
ただし、労働基準法26条が平均賃金の6割を休業手当として保証している趣旨に鑑み、控除できる金額は平均賃金の4割が上限と解されています(最判昭和37年7月20日)。
4.会社に休業手当や給料の全額を支払ってもらえない場合には?
会社都合の休業なのに、会社が支払うべき休業手当や給料を支払ってもらえない場合には、会社に対して支払いを請求する必要があります。
そのために取ることのできる手段について解説します。
4-1.会社と交渉する
まずは会社と交渉をして、休業手当や給料の支払いを要求しましょう。
新型コロナウイルスの影響により、雇用調整助成金の制度が拡大され、会社が労働者に対して休業手当などを支払うハードルは下がっています。
もし会社が雇用調整助成金の制度の利用を検討していないようであれば、制度の利用を進言することも有効かもしれません。
4-2.労働局の個別紛争解決制度を利用する
会社との直接の話し合いでは休業手当などの支払いについて合意できないという場合には、労働局の個別紛争解決制度を利用することも一つの手段です。
この制度を利用すると、労働局の紛争調整委員会のあっせんにより、専門家が労働紛争の解決を仲介してくれます。
当事者同士だけで話し合いをするよりも、客観的な第三者を間に入れて話し合いを行うことにより、より円滑に交渉が進むことが期待できます。
なお、個別紛争解決制度を利用しても合意に至らない場合には、労働審判や訴訟へと解決の場を移す必要があります。
4-3.労働審判
労働審判では、当事者間の合意が得られなくても、労働審判委員会による審判という形で解決策が提示されます。
労働審判は、訴訟よりも迅速な手続きにより行われ、原則として3回の審判期日を経て手続きが終了します。
4-4.訴訟
会社との話し合いによっては問題が解決しない場合や、労働審判の結果に不服がある場合には、最終的には休業手当や給料の支払いを求めて訴訟を提起する必要があります。
5.労働問題は弁護士に相談しよう
会社から休業手当を支払ってもらえない、あるいは給料の全額を請求したいという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
もともと、組織である会社と個人である労働者の間には、交渉力やマンパワーなどの観点から大きな差があります。
そのため、労働者が一人で会社に立ち向かうことは現実的ではありません。
法律の専門家である弁護士のサポートを受けることができれば、会社も労働者の言い分に耳を傾けやすくなり、会社に対する交渉力を大きくアップさせることができます。
また、労働紛争を解決するためには、会社との直接交渉から訴訟まで、段階を踏んでさまざまな手続きを取ることになります。
この点、早い段階から弁護士に依頼しておけば、交渉の状況などに応じた手続きの移行もスムーズに行うことができるでしょう。
何より、長年勤めていた会社と真っ向から言い分を戦わせるということは、労働者にとって非常に精神的な負担が大きい作業です。
法律の専門家である弁護士は、会社に立ち向かう依頼者の良き相談相手となり、依頼者の精神的負担を軽減してくれます。
会社に対する休業手当や給料の支払いを請求することを検討している方は、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。